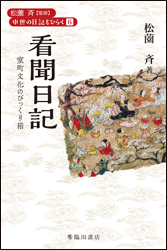|
中世の日記をひらく 全10巻 激動の日本中世史における重要な資料として知られながら、難読とされてきた漢文日記資料を精選。連続した期間のまとまった記事を抄出し、平易な現代語訳を提供する。中世を生きる人びとと、彼らがつくる政治・社会空間の息遣いが、いまここによみがえる! 3か月毎各回1〜2冊配本予定 ◎は次回配本 1 殿暦 摂関が記した武者の世前後 中丸貴史 著 2 長秋記 花園の守り人 栗山圭子 著 3 玉葉 九条兼実がみた武家政権の成立 長村祥知 著 4 公衡公記 鎌倉時代公武交渉の機微 山岡 瞳 著 5 花園天皇日記 鎌倉末期に生きる君主の生活と思索 坂口太郎 著 ◎6 看聞日記 室町文化のびっくり箱 ◎7 建内記 万里小路時房がみた室町幕府 8 御湯殿上日記など 戦国時代の宮中 遠藤珠紀 著 9 時慶記・晴豊公記 公家と武家を結ぶ人々 神田裕理 著 10 アンソロジー 残された珠玉の日記たち 松薗 斉 著
愛知学院大学教授 松薗 斉 平安時代の半ばから中世にかけて、数多く残されている貴族や僧侶らの日記は、この時代の具体的な歴史像を知るための重要な史料となっていることはいうまでもありません。ただ、それらの面白さは、史料としてだけではなく、この時代をそのままのぞき見ることができる「窓」として、そこから皆さんがよく知っている有名人のみならず、さまざまな人々の暮らしや生き様を直接垣間見ることができる点にあると思います。このシリーズは、この時代の歴史に興味がある方々に、専門の歴史研究者が選んだ断片的な素材ではなく、そのままのぞき込んで楽しんでいただくための手助けになることを期待して組んでみました。その「窓」からは、今とは全く異なる風景が目に飛び込んできて、びっくりされると思います。しかし、一方では、今とまったく同じように、男と女、家族や仲間たちとの喜びや悲しみ、トラブルや成功に一喜一憂する人々が生き生きと映し出され、遠い過去の人々に共感を持たれることも多いと思います。 中世古記録の世界へ 国際日本文化研究センター名誉教授 倉本一宏 中世の古記録(男性貴族が和風漢文で記録した日記)のみならず、日本の古記録研究の泰斗である畏友・松薗斉氏の監修によって、このたび、「中世の日記をひらく」全10巻の出版が開始されることになった。 国文学者 松尾葦江 学生時代からずっと、漢文日記を引用する際の解読には苦労してきた。いま一つ自信が持てない場合も多かった。人名や有職故実、歴史用語に暗いまま読むと、とんでもない誤解をしかねない。その一方、漢文日記はただの記録ではなく、人間味溢れる言述なのだとも感じてきた。『玉葉』や『明月記』など、記主の本音や処世法が吐露されているものはもとより、『百練抄』のような抄出集成本には、事実の取捨選択と意味づけを以てする、殆ど物語のような小世界が構築されている。 東京大学名誉教授 村井章介 日本中世の日記群は、日々書かれた原文の姿をよく残しており、自筆本が伝存する例もかなりある。明や朝鮮の「実録」が日次記の形式ながら完全な編纂物であるのと比して、アジア史全体のなかでも独特かつ貴重なものといえる。だがその記述は、記主の属する社会の「文法」(和様漢文という文体がその一例)に従って書かれており、現代人にとってとっつきやすいものではない。 |